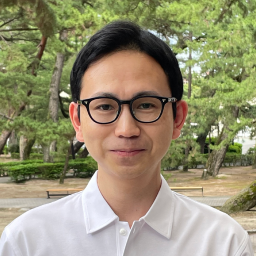社会の中の「耐えられないもの」に光を当てる
しかしそれでは、フーコーからは、ただ同じことを繰り返しているだけのように見えました。ブルジョワジーの正義からプロレタリアートの正義へと移っていったとしても、結局そこには同じような裁判の構図が存在している。中央に裁判官がいて、その両側に検事と弁護士、原告と被告人がいるという図式です。しかし、むしろ問題とすべきは、そうした裁判の構造それ自体、司法のテクノロジーそれ自体ではないか。そういうわけでフーコーは、そうしたテクノロジーと結びついた正義の観念それ自体を括弧に入れるようになります。
それでは彼は、正義の観念の代わりに、いったい何に依拠していくことになるのでしょうか。この点を見るためには、フーコーが1970年代前半に展開した監獄情報グループ(GIP)の活動を取り上げることが重要です。当時は、1968年5月革命以来の学生運動の流れもあって、学生や左翼の活動家たちがたくさん収監されており、彼らからは、一般囚ではなく政治犯の取り扱いをしてほしいとの要望が出されていました。当時の監獄の状況は極めて劣悪でしたので(悲惨な衛生環境、看守の過酷な取締り、囚人内でのリンチなど)、一般囚と同じ扱いだとあまりに耐え難かったのです。
彼らに対する支援の輪は監獄外に広がっていき、フーコーにもその輪に加わるよう依頼が届きました。その時多くの人が期待したのは、フーコーにもサルトルのように人民裁判を開いてほしい、そのための調査委員会を組織してほしいということだったのではないかと思います。しかしながらフーコーは、その期待には応えず、代わりに前述の監獄情報グループを組織し、新しい社会運動を展開することにしました。彼は、収監されている左派の友人知人たちの状況だけを改善させるのではなく、一般囚も含めた監獄の状況全般を問い直すために活動していったのです。
そしてその時におこなったのが、「耐えられないもの」についての調査と呼ばれるものでした。監獄をめぐる状況の中で、「耐えられないもの」、あるいは「受け入れられないもの」、「支持できないもの」などを調査し、情報を集め、世の中に発信していったのです。何か不正義を見つけて、それを告発し、裁判にかけるというのではなく、「耐えられないもの」を見つけて、それを詳らかにし、こんなことがあっても良いのかと社会に問うことをしたのです。既存の正義によって救済されるのであればまだよいけれども、そうした正義にさえ救済されない人がいる。しかも、彼らを救うための別の概念もなく、ただただその過酷な状況に放って置かれたままである。そうした事例を、既存のシステムの周縁、外側から調査して、光を当てるということをしたのです。
フーコーはそうして、監獄の耐えられない状況を明るみに出すべく、囚人たち自身に、自らの置かれた状況について発言する機会を与えていきました。ここには、知識人の活動に関する一つの新しい考え方が認められます。フーコーによれば、知識人は伝統的に、人間社会の普遍的な良心として、人民を代表したり弱者を代弁したりしてきました。それは「普遍的知識人」とでも言うべき存在で、まさしくサルトルによって象徴されるような人物です。これに対して、フーコーが新たに提示する知識人像は、自らが専門家として十分理解している範囲で社会問題に介入する「特殊的知識人」です。この新しいタイプの人物は、もはや弱者を代弁するのではなく、弱者自身に語る機会を与えようとします。「弱者は理性的に語る言葉を持っていないから無駄だ」と言うのではなく、彼らは彼らなりに合理的な思考を持っているので、それに言説の場を与える。そうすることで、これまで流通してはならなかったような言葉が初めて流通するようになり、既存の言説の秩序、知と権力のシステムは揺さぶられることになるのです。
藤田公二郎対抗主体化―ふてぶてしく存在する勇気
主体化のシステムに揺さぶりをかける対抗主体化
そのような耐えられないものや弱者の言葉が流通することで、言説の秩序自体が変わる。その人たちの喋り方や言葉遣いも含めて、今まで苦しみを生んできたシステムを相対化したり捉え直したりする。それは偶然的なシステムを変えられるアプローチにもなるように思います。
そこでシステムを変えられることと、そこから距離を取ることの難しさの中を抜けていく第三の道の可能性を伺えればと思います。それは藤田さんが言われる「対抗主体化」へと通じるものでもあるでしょうか。
山内泰「対抗主体化」については、今後考えていかなければならない問題だと思い、拙論「主体とは何か」の結論部分で、残された課題として記したのですが、「対抗主体化」という概念自体は、実を言うと、フーコーの言葉ではありません。フーコーは1984年に不慮の死を遂げ、道半ばで仕事が終わってしまうのですが、その彼の仕事を、残された世代が今後さらに発展させていくとすれば、どのようになるだろうかと考え、「対抗主体化」の概念を提案しました。
一般には、「脱主体化」の概念の方がよく使われているかと思います。近代のシステムでは、私たちの存在が近代的主体へと作り変えられる、すなわち主体化されるわけですが、それが息苦しくて耐え難いので、そこから何とかして抜け出さなくてはならない、つまり脱主体化されなくてはならないというわけです。これはこれでもちろん大事なことなのですが、しかしそれだけで十分かと言うと、必ずしもそうではないように思われます。当該システムから逃れて、脱主体化をし続けるだけでは、そのシステム自体を変えることはなかなか難しいだろうと思います。それにまた、人間の生はあまりに多面的なので、仮にその一面においてシステムの規範から脱し、自由になることができたとしても、その全ての面において、余すところなく脱主体化できるかどうかというと、実際問題としては甚だ疑わしいように思われます。それゆえやはり、たんに既存のシステムから逃れようとするだけでなく、今度は逆にそのシステム自体に揺さぶりをかけていくような働きも必要になってくるのではないかと思います。私はそれを「対抗主体化」という概念によって考えていければと思っています。
藤田公二郎ちなみに「再主体化」と言われるものは、どのようなものでしょうか?
山内泰再主体化とは、もう一度システムに組み込まれていくことです。いったんシステムの外に出たけれど、再びシステムの中に戻っていくことです。例えば、ジャック・デリダの脱構築のような方法では、主体/客体、能動/受動、公/私などのような二項対立のシステムをかき乱すように脱構築して、そうした主体/客体の分割以前にあるようなものへといったん立ち帰ろうとします。それは、ある意味では脱主体化されるということですが、しかし当の二項対立のシステムは、その後もすぐに再構築され、存続していくので、結局はまたそこに舞い戻っていくことになります。つまり再主体化されるということです。こうして脱構築と再構築、脱主体化と再主体化を幾度となく繰り返していくことになるわけですが、しかしそうした操作の背後にあって、当の二項対立のシステム自体は、結局のところ温存され続けることになります。脱構築が、ひょっとするとガス抜き程度の構造調整にしかなっておらず、むしろシステムの延命に手を貸しているかもしれない可能性について考える必要があるかもしれません。
藤田公二郎他律的な主体化と自律的な主体化
それでは対抗主体化というのは、偶然だからこそ変えていけることに依拠するあり方ですね。
山内泰そうです。既存のシステムの中で働いている主体化の場合は、あくまで自らの外部から押し付けられた主体化です。何か外側に規範があって、それに自らを合わせていくというものです。思考の規範もあれば、行動の規範もありますし、態度の規範もあるでしょう。フーコーの用語で言えば、知、権力、倫理の規範です。近代においては、それらに関して特有なタイプの規範が存在してきました。その規範にかなった者こそが、いわゆる近代的な主体、「理性的で自律的な主体」だったのだと思います。そうした近代的な主体化、人間学的な主体化に抗するものが対抗主体化です。
ここで、フーコーの「啓蒙とは何か」というテキストを参照したいと思います。よく知られているように、このテキストの大本はカントにあります。カントはフーコーに先立って、同じタイトルの論文を1784年に書いており、そのちょうど200年後の1984年に、フーコーが同じ問いを取り上げ直して、論文を執筆しているのです。それは、カントの啓蒙論を読み直して、その歴史的意義を再評価するとともに、それに新たな可能性も付与しているような論文です。
このテキストの中でも、外部から押し付けられた主体化が話題になっていると言えます。すなわち、自分が何かをしなくてはいけない時に、自分の頭で考えるのではなく、外部の権威の言いなりになっているような状態が問題視されているのです。例えば、「書物」の言っていることを鵜呑みにしたり、いつも「精神的指導者」の指示通りに行動したり、「医者」に自分の生活を丸ごと管理してもらったり、というように。これはつまり、外部から課された人間の規範に従って生きているような状態です。
近代ではしばしば、こうした過程を通じて自律的な主体が立ち上がると考えられてきました。しかしながら、そこではあくまでも外部から規範が押し付けられており、実際には自律という名の他律であると言えます。その限りにおいて、既存の主体化を他律的な主体化と言ってもよいかもしれません。それは、システムの規範を遵守するような主体化です。
これに対して、対抗主体化と呼び得るものの特徴は、そうした所与の規範を批判的に吟味して、それが本当に必然的なものなのかどうかを自ら検討していくことにあります。そして、もしそれが必然的なものでなければ、その恣意的な拘束力から自由になって、自身を新しい存在へと練り上げていくのです。すなわち自律的な主体化です。所与の規範をたんに維持しようとするのではなく、自ら規範を創設していくような主体化です。
藤田公二郎新たな公的活動に向けて
このフーコーの論文を、今回いただいたテーマ「公と私」にもう少し引きつけながら、話を続けてみたいと思います。今回のテーマでは、伝統的な公/私の対立システムを批判的に捉え直しながら、その対立の彼方で、新たな公、あるいは新たな私を構想していくことが問題になっているのではないかと思います。フーコー自身は、公/私の対立を直接議論することはあまりなかったように思いますが、しかし見方を変えれば、彼は実のところ、公/私の対立をずっと問題にし続けてきたと言うこともできるように思われます。
実際、今回最初に触れていただいた拙論「生命的−主権的複合体」では、そのことが潜在的に話題になっています。ここではその議論に詳しく立ち入ることはできませんが、私がそこで提案した概念「生命的−主権的複合体」とは、つまるところ、フーコーが「生権力」と呼んでいるものと「主権権力」と呼んでいるものの相互補完的なシステムのことです。その主権権力の側がもっぱら公共領域、生権力の側がもっぱら民生領域に関わっている限りにおいて、そこでは結局のところ、公/私の対立システムが問題になっていると言ってもよいかもしれません。フーコーはもちろん、主権権力の側にも生権力の側にも肩入れすることはありませんでしたが、それはおそらく、両者が相互補完的なものだったからではないかと思います。そういう意味では、既存の公/私、いずれの側にも支えを見出せなかったということです。フーコーは、そうした公/私の対立システムの外側へと向かい、そこで新たな公的活動について考えようとしたのだと思います。そうした試みを、まさしくフーコーの啓蒙論文、カントの読み直しの内に認めることができるように思うのです。
カントは啓蒙を一つの運動として捉え、「未成年状態からの脱出」と定義しました。啓蒙とは元々、理性の光によって蒙を啓くということですが、そうした啓蒙以前にある人は、いまだ自分の理性を自分自身で使用することができず、先ほど触れたように、書物や精神的指導者、医者の言いなりになって生活しています。つまり未成年状態にあるということです。その状態から脱して、成年へと移行することがまさしく啓蒙なのです。それはつまり、自分の頭で考えて行動するということです。カントはそれゆえ、あの有名な啓蒙の標語、「知る勇気を持て(sapere aude)」と言ったのです。
ところで、カントはその際、理性の私的使用と公的使用を区別しています。一般的には、理性の私的使用と言うと、休日のプライベートな時間に頭を働かせること、理性の公的使用と言うと、平日仕事をしている時に頭を働かせることをイメージするのではないでしょうか。しかしカントは、それとは真逆のことを言っていて、フーコーはその点に大きく注目しています。カントによれば、仕事をしている時は、何か与えられた役職があって、その限定された目的を達成するためだけに理性を使っています。それは理性の限定された使用、特殊的な使用であって、結局のところ私的な使用に過ぎません。しかし、休日はそうした職務から解放され、理性を自由に、普遍的な仕方で働かせることができます。それこそが、理性の公的な使用にほかならないのです。
藤田公二郎