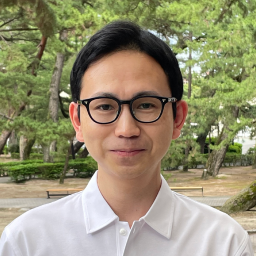それに関して、次に現代の知と権力の構造を、どのように相対化する可能性を見出せるかについて伺いたいと思います。藤田さんは「主体とは何か」の最後で、「人間学のまどろみ」に囚われないようにしながら、私たちを主体化させていくシステムを描き出そうと言われます。そのように主体化を要請してくる社会システムへのアプローチについては、フーコーの言説や言表の「考古学」という考え方にヒントがあるのでしょうか。
山内泰「考古学」は、フーコーの重要な歴史研究の手法です。彼はこの考古学と、もう一つ別の歴史研究の手法、ニーチェの「系譜学」を組み合わせて仕事をしています。考古学の方は言説や言表などの知の問題を扱い、系譜学の方は権力の問題を取り扱うものです。
考古学とは「アルケオロジー」の訳語で、元々は起源学という意味です。カントのテキストに「理性の考古学」に関する議論があって、フーコーの考古学も当初は、そのカントの考古学、つまりは近代哲学に根差した「超越論的な考古学」の影響を受けて、理性の起源にまで立ち帰ろうとするものでした。理性の目的論的進歩の起源です。しかしそれでは、フーコーがその後批判していく近代の枠内に収まってしまいます。ですからフーコーは、その超越論的考古学から出発しつつも、それを内在的に批判することで、全く異なる考古学へと移っていくことになりました。拙論「主体とは何か」では、それを、言うなれば、「主体の哲学」のパラダイムから「主体化の哲学」のパラダイムへの転換として分析しています。実際フーコーはその時、考古学をもはや「起源を探究する学問」ではなく、「アルシーヴを探究する学問」として再定義しています。アルシーヴとは古文書のことで、つまりは知や言説、言表を意味しています。
もう一方の系譜学は、ニーチェに由来するものであり、これは当初より、起源の探究に対立する知として展開されてきました。歴史の起源は単一なものではなく、実際には複数の起源が存在している。だから系譜学は、私たちの世界の唯一純粋な起源を明らかにしようとするのではなく、その多様で複雑な由来や来歴を暴き出そうとするのです。そしてまた、そこから逆に、そうした由来や来歴が、歴史の様々な権力関係、力の闘争を通じて、どのように現在の世界を作り出すことになったのかを明るみに出そうとするのです。現在から出発しつつも、その現在の状況が生まれてきたのはどのような力の闘争によるものなのかを明らかにするべく、過去をたどり直していく。だからフーコーは、「現在についての歴史」という言い方もしています。それはつまり、当たり前となった現在を批判的に問い直すための歴史なのです。
藤田公二郎システムから出発しつつ、システムを批判的に記述する
今回のテーマでは、伝統的な「公/パブリック」と「私/プライベート」の枠組みに内在しつつも、それを批判的に捉え直すことが問題になっているのではないかと思います。この内在的批判をめぐっては、フーコーの仕事が、私たちに一つの興味深い方向性を指し示してくれているように思います。考古学者や系譜学者も、当然ながら、最初は既存の知と権力のシステムの真っただ中にいます。しかし、そのシステムにどっぷり浸かっていては、システム自体を自覚することは難しいので、何とかそれに対して一定の距離を取ろうと試みます。当該システムからたとえ完全に外に出ることはできなかったとしても、そのシステムの周縁や限界、あるいは内と外の境界へと赴くよう努めるのです。そうすることで、システムから出発しつつも、そのぎりぎりのところでシステムを何とか対象化し、批判的に記述することができるようになるのです。
もちろん、その試み自体も決して容易なものではありません。最初は、考古学者や系譜学者自身も、既存の知と権力のシステムにどっぷり浸かっているので、当然ながら、彼らの手持ちの道具自体も、総じてその同じシステムの内に属しています。ですから、その手持ちの道具を当たり前のものとして使用し続けている限りは、当該システムを平常運転させていることにしかならず、そこから距離を取って批判的に分析することはできないのです。そのため、まずはその手持ちの道具自体を括弧に入れて、むしろそうした知が、既存のシステムの一部としてどのように歴史的に成立し、これまで機能してきたのかを検討することが重要になってきます。
例えば、近代人が最も頼りにしてきた道具の中に、「理性」や「人間」といった人間中心主義的な概念があります。こうした所与の概念を分析道具として歴史を検討したならば、「理性」がいかに目的論的に進歩してきたか、「人間」がいかに野蛮状態から脱し、文明化してきたかという話になってしまいがちです。これでは、先ほど見た「大きな物語」の議論に立ち返ってしまいます。ですので、むしろそうした人間中心主義的な概念が、いかに歴史の中でたまたま出現し、大きな影響力を持つに至ったかを検討することが重要になってきます。フーコーが一連の著作で明らかにしたように、「理性」が一七世紀に狂気を排除することによって成立したとか、あるいは「人間」が一九世紀に規範化のシステムを通じて誕生したとか、そうしたことを記述していくことになるのです。「理性」や「人間」といった普遍概念によって歴史を説明するのではなく、反対に歴史によってそうした概念の偶然性を説明するのです。そうすることで、考古学者や系譜学者自身、「理性」や「人間」のような固定観念から解放されつつ、それらの観念が属している知と権力のシステムを描き出すことができるようになるのです。
もっとも、こうした作業は一挙に果たされることができないだろうと思います。というのも、手持ちの道具を全ていっぺんに括弧に入れたならば、もはや分析のための道具が何も残されなくなってしまい、そもそも分析自体が不可能になってしまうからです。それゆえ、何らかの概念は括弧に入れても、別の概念は使い続けなくてはならない。むろん、その別の概念もまた、一定の歴史性を帯びたものであるので、それで描いた歴史記述も、依然として中立的なものではあり得ません。しかしながら、そうした作業を際限なく繰り返し続けることで初めて、私たちの知と権力のシステムを多面的に、多層的に描き出していくことができるようになるのではないかと思います。そうすることで、私たちは徐々に、そのシステムの囚われから自由になっていくことができるのではないかと思います。
藤田公二郎現代の規範システムの中で、「耐えられないもの」に気がつくこと
「正義」では救えないもの
そのような考古学・系譜学は、規範的な人間を作るため、正常な人間として主体化が求められるシステムに対して、どう距離を取ることができるか、さらに伺いたいと思います。主体化を促すシステムの中で、主体が苦しいと思うあり方は、例えば学校や会社などどこにでもあると思います。それを主体からの視点ではなく、それを生み出すシステムの側を変えることで緩和するにはどのようにすればよいでしょうか。
山内泰先ほどは、いかにしてシステムから出発しつつも、そこから何とか身を引き剥がして、それを記述していくかという話をしました。今度は、そこで記述されたものについて、どのように評価するか、価値判断するかが問題になってくるかと思います。否定的に評価されるものについては、変えていこうということで。その際、その価値判断の根拠がどこにあるのか、まずは問われることになるのではないかと思いますが、そこで、「耐えられないもの」という言葉がキーワードになってきます。
一般的には、社会の良し悪しは、正義にかなっているかどうかで判断されることが多いのではないかと思います。しかしフーコーは、この「正義」という観念自体も、実のところ、知と権力のシステムの内にあって、その歯車の一つをなしているのではないかと考えました。場合によっては、現行社会の中で正義として働いているものも、一部の人には大変息苦しいものであるかもしれず、彼らの生存を追い詰めているだけかもしれないということです。
フーコーが正義の観念を頼りにできなかったのは、彼よりも一つ年上の世代の哲学者、ジャン=ポール・サルトルの活動に疑問を持ったことがあるからだと思います。フーコーが権力の問題に関わり始めた1970年代、サルトルはすでに西洋を代表する知識人で、社会問題に広くアンガージュマンしていました。
例えば、当時フランスの地方都市ランスでは、石炭会社「北部炭鉱」の坑道内でガス爆発が起こり、労働者に多数の犠牲者が出る大きな事故がありました。毛沢東主義の活動家たちは、そうした事故が劣悪な労働環境下で起こったことに抗議し、同社に火炎瓶を投げ込んで逮捕者が出るなど、大きな社会問題に発展していました。
そこでサルトルは人民裁判を開くことにしました。彼からすれば、既存の裁判で裁くことは、あくまでブルジョワジーの正義によって裁くことに過ぎず、資本家側の立場から事態を収拾することにほかなりません。ですので、ブルジョワジーの正義によってではなく、いっそう人民に根差した正義、プロレタリアートの正義によって裁こうとしたのです。既存のシステムの中にある正義が不十分だから、その正義の概念をさらに根本的なものへと磨き上げて、人民の正義で裁こうとしたんですね。
藤田公二郎